これからの時代にあるべきショールームの姿とは ウィルクハーン・ジャパンが新オフィスの空間に込めた思想

2024年3月、ウィルクハーン・ジャパンはオフィス兼ショールームを赤坂に移転しました。以前までの地下フロアと異なり、ビル7階の窓からは赤坂御所や新宿御苑までを見渡せる、開放的で四季折々の光にあふれた空間です。ゾーニングの最大の特徴は、オフィス空間とショールーム空間が一体となっていること。ゆるやかなエリア分けがされつつも「オフィス家具にとって、実際に使われているシーンを見ていただくことに勝るプレゼンテーションはない」という発想が込められています。ウィルクハーン・ジャパン内の移転プロジェクトチームと半年以上のディスカッションを重ねながら、空間デザインを担当したアーキタイプ主宰の建築家・荒木信雄氏に、その狙いを詳しく聞きました。
空間の主人公は「人」と「家具」
――荒木さんは、1990年代から現在まで、東京を中心とした都市の商空間を彩ってきた建築家です。その一方で、オフィス空間もかなりの数を手掛けられているのですか?
少ないながらご依頼はいただいています。僕はオフィスでも、商空間でも、住宅でも、家具などのプロダクトでも同じスタンスで臨むので、あまり区別はしません。シンプルにその場の最適解としての空間を理詰めで考えます。もともと都市計画の出身ですから、ロジカルなやり方が性に合っているんですね。

Photo:Teppei Tanimoto
――これまでに荒木さんが手掛けた作例のうち、メディアによく登場するオフィスには「吉本興業 東京本部」(2008年)があります。
これは1934年に建てられた旧四谷第五小学校を改修した空間ですが、現存する日本最古の鉄筋コンクリート造の小学校校舎です。近代建築の記録と保存を目的とした国際学術組織である「DOCOMOMO(ドコモモ)」の日本支部が選定した、国内におけるモダン・ムーブメントの建築100選にも選ばれています。以前は自転車置き場になっていた中庭は芝生を植えるだけの変更に留めるなど、モダニズムから生まれたデザインをなるべく生かそうと考えました。
ここに誰もが見たことがあるだろうフリッツ・ハンセン社の「セブンチェア」(1955年、デザイン:アルネ・ヤコブセン)を置いています。さらに「吉本興業 大阪本部」(2010年)にはウィルクハーン製品の「FS-Line」を置かせてもらいました。
僕がつくる空間は、「物足りなさ」を感じることが多いかもしれません。その余白に「人」と「家具」が収まって、初めて完成するからです。よく半ば冗談で言うのですが、空間デザインの役割は、プロジェクト全体の2%くらいの要素でしかありません。一番重要なのは、やっぱり人。その次に、空間を構成する必要不可欠な部品としての家具があると考えています。
空間の主役は人だから、そこに置かれるのは「ごく当たり前にありそうな佇まいなのに、よく見るとつくり手の想いと機能のバランスが良い家具」がいい。そういう意味で、セブンチェアやFS-Lineなどの「マスターピース的な家具」を採用することが多いですね。
――今、お邪魔している事務所でもFS-Lineを使っています。これらの椅子を、荒木さんがマスターピース(傑作)と捉える要素は、何ですか?
まずは、しっかり「つくり手の意思」が伝わってくることでしょうか。そういう意味で、若手の方がつくる家具でいいと思うこともあります。ただし、あくまでも自分の中でマスターピースだと評価するのは、「時代の風雪に耐えて、世の中に適応している家具」。「ごく当たり前にありそうな佇まいなのに、よく見るとつくり手の想いと機能のバランスが良い家具」です。
――なるほど。もはや環境の一部を当たり前に構成しているような、さりげない家具がマスターピースということですね。

Photo:Teppei Tanimoto
海外の空港やいろんなオフィスで、FS-Lineが使われているのは知っていました。初めて購入しようと訪れたのは、六本木のAXISビルにあったウィルクハーンのショールームです。ショールームに行くと、スタッフが歴史を語ってくれるわけです。どこにでもありそうな形なのに、わざわざそれを長年つくっている。今は色味が変わってしまいましたが、金属製フレーム・ベースに粉体塗装された「絶妙な白の色味」をとても気に入っていました。これは自宅で使い続けています。
ウィルクハーン製品の場合、もちろん家庭よりオフィスで使われることの方が圧倒的に多いはずです。だから今回のプロジェクトでは、「リアルなオフィス家具」を見せるという見立てで、ショールームとオフィスを重ね合わせる提案をしたのです。

Photo:Lemmart
境界をあえて設けないゾーニング
――今回の移転プロジェクトは、前にショールーム兼オフィスが入居していたビルに建て替え計画が持ち上がったときからスタートしました。あらためてどのような経緯で進んだのでしょうか。
2023年の夏前に声をかけていただき、真夏の頃にキックオフした短期決戦プロジェクトでした。一般には「何人くらいの従業員がいて、何部屋が必要でしょう」と聞いていく設計者さんもいらっしゃると思いますが、僕のやり方は「そもそも新しいオフィスは必要ですか?」といった、そもそも論から始めます。
しかし、実際には引っ越しすることは必須条件で、移転先の物件も決まっていました。わざわざエレベーターで上がっていく予約制のショールームになることをどう捉えるか。いろんな空間デザインのパターンについて、ウィルクハーンのメンバーたちに一緒に考えてもらい、ディスカッションしました。
僕からは「この半年強という設計期間が、自分たちの空間の『取扱説明書』だと思ってください」とお願いしました。「自分ごと」として捉えた途端、いかに設計という行為が難しいかもわかるし、お客さんの視点も、そこで働く自分たちの視点も持てるんですね。

Photo:Lemmart
――チームメンバーとの議論で、印象に残ったやり取りはありますか?
例えば、住宅でいう「ダイニング・キッチン」のように何となくみんなが集まる場所がつくれないかという問いかけがありましたね。そこで、自分たちの好きなシーンを設定してもらいました。例えば「住宅でダイニング・キッチンが果たす役割を、もしオフィスに落とし込んだらどうなるだろう?」といった会話をしました。
あとは「街」や「公園」という比喩も出ましたね。公園で子どもたちが遊び方を勝手に発明していくように、空間の使い方は入居後に決めていければいい。その結果、ある程度のゾーン分けのみをしておき、さらに大きな箱と小さな箱を置いておけば、どこのオフィスにもありそうなシーンは再現できるという立て付けになりました。
全体を20人の従業員だけで使うには贅沢な広さの空間です。1日のうち居場所を何回も変えるといった使い方もできる。あるいは、いろんな人に期間限定で貸したり、他社の従業員と少しだけ一緒に働いたり、そんなプラットフォームとしての場になればいいと思うんです。

Photo:Teppei Tanimoto
余計な足し算をしないのが肝心
――入れ替え用の商品などを一時保管するバックヤードを除けば、本当にショールームとオフィスの境界がないので、パブリックとプライベートな空間が溶け合った公園のようです。オープンに見せる部分、半分クローズにする部分はカーテンを引いて仕切れるようになっていますね。
僕はクヴァドラ社のファブリックを使うことが多いのですが、ウィルクハーンの椅子にも相性が良さそうだと考えたのもあり、同社のカーテン生地を選びました。遮光カーテンみたいなものより、何となくうっすら影がわかるようなものがいい。いくつか見させてもらったうち、透け感とクローズ感を絶妙にグラデーションとして出せる新作があったので採用しました。

Photo:Lemmart
――オフィスビル然とした壁紙や天井などは、パッと見ると何もデザインを施していないのではないかと思うほどです。これは、顧客のオフィス環境を考えてのことですか?
それもあります。床は白にすると汚れると思いましたが、壁に関してはあまり選択肢がありませんでした。プロダクトの方に目線が行ってほしいので、意識を極力させたくないという直感的な雰囲気で白にしたわけです。どこが新しくて、どこが以前まで使っていたクロスか、お客さんにわからないくらいが丁度いい。天井に関しては、ビルオーナーさん、あるいは他のフロアの入居者にしか変わったところがわからないと思いますが、実はかなり複雑な工事をしました。
僕はよく「ミニマリスト」と言われたりしますが、どちらかと言えば余計な足し算をしないだけで、引き算をしたいわけではありません。同様の思考に基づくドイツのモダニズム建築には強い影響を受けました。特にチェコの「トゥーゲントハット邸」(1930年、設計:ミース・ファン・デル・ローエ作)には、2001年に世界遺産へ登録された際の改修前と後、何度か訪問しています。
トゥーゲントハット邸は単なるガラスの箱とも思える、簡潔な外観をしています。しかしシンプルにつくられているからこそ、さまざまな用途で使い継がれ、時代に翻弄されながらも今日まで生きながらえている。「Less is more」はよく使われる言葉ですが、トゥーゲントハット邸からは、「少ないことの力強さ」を強く感じます。これは今回のショールームの考え方にもつながっています。シンプルなつくりだからこそ、可変性が極大になる。将来の需要にも耐え得るということです。
余計なもの、必要じゃないものは空間になくてもいいんじゃないか。その想いは年を追うごとに強くなってきました。これからの時代のショールームも、やっぱり人が主役だと思います。家具と人だけ存在していれば、その空間が風化することはないですから。

Photo:Teppei Tanimoto
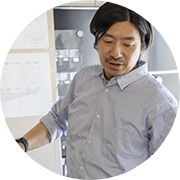
荒木信雄 / Nobuo Araki
1967年熊本生まれ。1990年西日本工業大学建築学科を卒業。その後、豊川建築研究所を経て1997年The Archetype設立。
現在、西日本工業大学客員教授。
主な仕事に、吉本興業株式会社 東京本部、Ginza Sony Park、 The Mass / StandBy など。
The Archetype WEBサイト
インタビュー・文:神吉弘邦 Interview and text:Hirokuni Kanki

